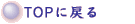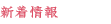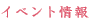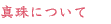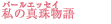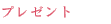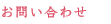|
◆パールの心 渡辺 昭子
二十歳のお祝いに、無口な父が初めて私に手渡してくれた宝石は、パールのネックレスでした。
青いベルベットのケースに入っていた真っ白いパールは、深い海の底に眠る貝のように真っ白く輝いて、いっそう純白に見えました。
その時、遠い夏の日のことが、私の頭によみがえってきました・・・・・・。
それは、私がまだ十歳の頃、夏休みに一人で田舎に出かけた時のことでした。
田舎のバスは、待ちきれませんでした。
一時間に二本ほどしか通っていなかったからです。
待ちぼうけした私は、バス停の前の砂浜で貝殻を拾いながらバスを待っていました。
汗ばんだ手に小銭を握り締め、赤いスカートのポケットは、拾ったピンク色や白い貝殻で溢れていました。
三十分くらい経った頃、バスは来ました。私の後ろにはもう二人ほど大人が並んでいました。
やっと着いたバスに急いで乗りこんだ私は海側の席を取ろうとして、慌てて駆け出しました。
その時、ジャリとして、車内いっぱいに、私のポケットの貝殻が勢いよく飛び出してしまったのです。
貝殻はバスいっぱいに散乱してしまいました。
まるで、節分の豆まきをした後のようでした。
一瞬、バスに乗っていた大人たちの怪訝そうな視線が、私を取り囲んだのを感じました。
きっと、ゴミでも投げ捨てたように見えたのだと思います。
私は真っ赤になって、泣きそうになり、どこから拾っていいかもわからず、立ちすくんでしまったのです。
その時でした。
真っ白なブラウスを着た若い女の人が、私の側に駆け寄って来ました。
そしてすぐさま、小さな貝殻をさっと拾い集め、「はい。宝物」と言って、私のポケットにそっと戻してくれたのです。
お姉さんの首筋に純白のパールがまぶしく揺れていました。
潤んだ瞳で見つめたパールは、まるで水の中で優しく揺らめいているように見えたのです。
それは、私のポケットの貝殻よりも、数倍も輝いて美しかったのです。
私はろくにお礼も言えずに、お姉さんの首元の輝くパールを見つめながら、小さくお辞儀をしていました・・・・・・。
なぜでしょう。
今となっては、その人の顔すら思い出せないのに、あの時の上品で涼しげなパールが、いつまでも心に焼き付いています。
いつか私も、あんな素敵なパールが似合う大人になろうと心に決めていました。
それが二十歳になって、大人の仲間入りをした私に、やっとその時がきたのです。
思えば、宝石というものは不思議です。
人を上品にも下品にもしてしまうからです。
きっと、父のくれたパールにも、他の宝石では表現できない、言葉よりも的を得た、父のメッセージがこめられていたように思います。
真っ白なパールの粒の中に、いつまでも上品で正直な、優しい女性にと・・・・・・。
あれから、二十六年、主婦歴も長くなり、平凡に暮らしていますが、例え、ティーシャツとジーパンの日常でも、首元だけは小さなパールを揺らして、密かに女性の生き方を自己主張しています。
(「パール・エッセイ集」の作品より)