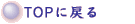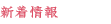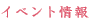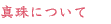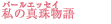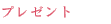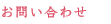|
◆架け橋は真珠色 きくきみえ
「なんかあったん」
そうたずねないわけにはいかないような恵比須顔で、母は私を迎えた。いつもは「おかえり」どころか「帰っとったんか」の山の母が、だ。
「つかれたぢゃろう」
その日は「まあ、おすわりぃ」といってお茶までいれてくれた。
ちゃぶ台に正座した母のにこにこ顔からこぼれた言葉は「あんたがくれたアレなあ。秋美さんに、やったが」だった。わたしが怒るとでも思ったのか、母はわたしの顔色をうかがいながら慎重な話し方をした。
秋美さんというのは兄嫁のことで、あげた、というのは、わたしが母の日のプレゼントに、と勤務先の慰安旅行で伊勢、志摩にいったときに買ったペンダントのことだ。銀メッキの鎖に、待ち針のあたまほどの真珠でこしらえた蝶がぶらさがっていた。
「こねえな(こんなに)黒え顔で」とか、「ええトシして」とか、いつもの調子で一通り御託を並べると、母は「あんたしねえ(しなさい)」と、ろくに見もしないで、ちゃぶ台のうえをわたしに押し返した。
父は生前、そんな母をよく叱った。こどもが折角買ってきてくれたのに、なんで素直に喜べんのぢゃ、と。
そのときは、悪かった悪かったと平謝りの母だが、次のときはもう忘れている。
父の死後、六反の畑を独りで耕しながら、田んぼの草を取りながら、母は末娘のわたしがきれいになることだけをたのしみにしてきた。そのことはわたしが一番よく知っているはずなのに…。
かあさんのあまんじゃく、母さんの強情っぱり、と母を恨みながらも、ほおを流れ落ちるなみだは母の気持を想いつつ、わたしを責める涙でもあった。
旅先のみやげ物店で、出張先の駅の売店で「母にどうだろう」と真っ先におもうものの、母のいつもの態度が見え隠れして、高価なものには手が出せなかった。でも、あたまから手ぬぐいを取って、地下足袋を脱いで、町の子のお母さんのように、白いブラウスのえりにネックレスを揺らす。わたしの頭のなかには、そんな夢のような母がいつもいた。
ペンダントをもらった兄嫁は「こんなのほしかったの」とねだり、「かわいいわぁ」と胸に当て、「大事にする」といったという。
わたしは、「えっ」と飲みかけのお茶をちゃぶ台のうえにもどした。
都会育ちの兄嫁はオシャレだった。無理をしている兄嫁が気の毒になったのだ。
わたしの思いとは裏腹に、兄嫁はそのペンダントをいつも胸もとで光らせていた。冬はとっくりとセーターの胸に、夏はタンクトップの襟ぐりに。そして、こくびをかしげては「きみちゃん、ごめんね」という。
そこには姑からもらったから仕方なくしているという素振りはまったく見られなかった。なによりも、似合っているのだ。兄まで視線を兄嫁の胸にやり、目を細めている。
義理が大きく働いたみやげで、とても自分自身がつける気にならなかった安もの。でも、どうして兄嫁にはあんなににあうんだろう。いつもわたしは考えていた。
その後、仕事の関係で引っ越した兄夫婦は休みごとに、母とわたしを気遣って帰ってくれた。手作りのいなり寿司に、サンドイッチに、お好み焼き持参だったこともある。
煮物にしてくれとか、カレーはやめてくれとか、注文の多い母だが、兄嫁の持ってくる手料理に文句をつけたことがない。ほんとうにおいしそうにいただく。ついわたしのほうが「かあさん。コレだいじょうぶぅ」と、普段、胃もたれを訴える母を横目でうかがったこともある。
母は油でギトギトした鶏の唐揚げをほおばり「でえじょうぶぢゃあ。大根おろしゅうたっぷりつけてくれとるけえ」と屈託がない。それどころか、案じるわたしに対して、へんなことをいようらあ、この子ぁ、せっかく秋美さんがつくってきてくれたゆうのに、という感じでわたしを見る。
料理とともに嫁の気持をいただいている母なのだ。そう、兄嫁が母からもらった真珠のペンダントを大切にするのと同じ気持の色。ふわあっと暖かで、淡いピンクに見えたり、クリーム色に見えたりする心の色、真珠色。互いが通じ合う色とでもいったらいいのだろうか。
娘が一人増えた、がくちぐせの母。
二十数年がたった今も、「お母さんは自分の娘にもらったものまで嫁のわたしにくれた」と、両頬にえくぼをこしらえる兄嫁。
二人の間に立って、なんとなく疎外されているような自分の存在に、母のしあわせを感じてならない。
真珠のペンダントが懸けてくれた橋、粋な計らいに感謝。
(「パール・エッセイ集」の作品より)