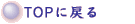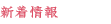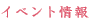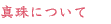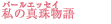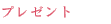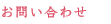|
◆真珠の涙 平岡 周五
あれは五年前の春まだ浅く、梅のつぼみがほころび始めた頃であった。
当時、幼稚園児であった孫娘が、不幸にも急性リンパ性白血病と診断されて、緊急入院してしまった。
それまで白血病と言う病は、聞いたことはあるが所詮余所事に過ぎず、況してや内の孫が、小児人口十万人に三十四人の発生率という難病に、選りに選ってなるとは夢にも思わず、涙は涸れるばかりであった。
入院以来、大人でもその苦痛に耐え難いと言われる、抗がん剤による化学療法を苦しささえ十分に表現することもできぬまま、毎日小さな体ひとつで、泣きもせず必死に耐え忍んでいた。
その内に、抗がん剤による副作用なのか、お多福のように腫れてくる自分の顔を、不思議そうに鏡で眺めるとともに、脱毛により地肌が見えるようになってしまった頭を、時に窓ガラスに映しては、点滴チューブがつながれた、か細い手で撫でながら、
「毛がとれちゃったよ」
と自分が今、先の見えない、どれほど重病の身であるのかも知らず、無邪気にはにかむ孫の冴えない顔を見るのは辛く、さりとて抱いてやろうにもクリーンルームの、ビニールカーテン越しでは為す術もなく、いとおしく不憫で心が疼いた。
そんな入院生活の中にも、四月末、五歳の誕生日をベッドの上で迎えた日、通園していた保育園の園長先生と保母さんが、ご親切に千羽鶴と『幼稚園』という本を持って、見舞いに来て下さった。
孫は早速、本の付録を開けてその中から、大粒の真珠のネックレスを見付けて取り出すや、体のしんどさも忘れ、にこにこしながら首に掛けて鏡を見た。
そして、子ども心にもよほど寂しくて、保母さんや友達に会いたかったとみえて、どこで覚えたのか、年齢にも似合わない老成した言葉で、保母さんに、
「涙の出るほどうれしい」
真珠のネックレスに、指先を触れさせながら微笑み、周囲を和ませた。
居合わせた若い看護士さんが、
「まあ!きれいだよ。良く似合うわよ」
そう言いながら、目を潤ませた。
孫はクリーンルームの中での、一人ぼっちの苦しい闘病の中、健気にも笑顔と感謝する心を忘れてはいなかった。むしろ笑顔を忘れていたのは、終始笑顔で励まし、看病してやらなければならない立場の、家族であったことに気付かされた。
五箇月間にわたり全国の見知らぬ献血者の、尊い真っ赤な愛を戴きつつの治療とともに、
―たった一日でもいいから、小学校へ行かせてやって下さい―
と、朝に夕に神仏にも祈り続け、なんとか逐次好転し、夏の初めには無事退院することができ、じ後は通院となった。
その後お陰様で、桜の花吹雪が祝福してくれるかのように舞う中、晴れて小学校に入学でき、赤いランドセルは母親に持たせて、よたよたながらも一日行っては、三日休むような状況ではあったが、それでも現在元気に四年生となることができた。
しかも、白血病患者の五年生生存率数十パーセントを、あと半年でクリアできる所まで漕ぎ着けて、高波を受けた運命を乗りきって行く、光明が明明と見えてきた。
そうなると次には、
―どうか二十歳の成人式を元気に迎えさせてやって下さい―
と祈願するところである。
幼稚園児であった入院中に、
―涙の出るほどうれしい―
と喜んだ、あの本の付録の真珠のネックレスは当然のことながら子ども騙しの、模造真珠であった。
だから、孫が懸命に生きて迎える二十歳の春を、今度は何が何でも、あの奥ゆかしくも気高く、しかも控え目に輝く、本物のアコヤ真珠のネックレスで、祝って飾ってやりたいと、心から念願している。
そして、今からその十年先のことを、祈るがごとく、あるいは夢見るように想像することがある。それは孫の首に、ふくよかにして美しく、温かみのあるアコヤ真珠のネックレスを、そっと付けさせ、
―これからも元気で、このアコヤ真珠のように、美しい人生を歩んでおくれ―
と、そう言ってやりたい。
ひょっとしたら、その時は孫とともに、真珠の玉に似た、熱い涙を流すに違いない。
(「パール・エッセイ集」の作品より)