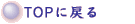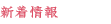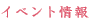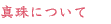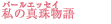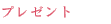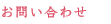|
◆沈黙の真珠 松本藍
駅の改札口を通り、バスの停留所へ向かおうとして気付いた。
雨。
大粒の、勢いのかなり強い雨が降っている。夕立だからすぐに止むだろうと、駅前のパン屋で買い物がてらしばらく待っていたが、あてが外れ、十五分経っても止む気配がない。
いいや、濡れたって。
その頃、私は日常生活で嫌なことがあって、自暴自棄になりかけていた。だからというのではないが
(雨に濡れるぐらい、今の心境に比べたら大したことじゃない)
パン屋を出て、店の屋根の下を進むのではなく、走るのでもなく、ざんざん降りの道路の中央を歩き出したのだ。
開き直って雨に打たれながら歩く私の横を、迎えに来た車や、傘の柄にしがみつくようにして足早に進む人、できるだけ濡れないように体をかがめながら走る人たちが通り抜ける。ときどき、その勢いで水がかかったが、気にも止めなかった。これだけ濡れたんだ、どこまで濡れたって同じだ。すてばちな、ヤケを起こしたような気分で、少しでも濡れるのを防ごうとする人たちが妙に小さく、おかしく思えたのだ。 駅からかなりの距離があるが、停留所は駐車場の向こうにあるため、バスが来てるかどうかはすぐわかる。待つ人の列を見ると、バスは出たばかりのようだった。
「ついてない」
雨が降った時点でそうか-いや、もともとだな。あと五分ほど来ないなら、急ぐ必要もない。
さらに歩調を緩めていったので、バスを待つ人の列の後ろについたときには、その列自体がベンチつきのアーチからはみ出るほどの長さになっていた。
私が並んだ後もすぐ人が並び、列はまだまだ長くなりそうな気がする。この分だと乗るの、二台目になるかなぁ。前の人たちが乗ったら、詰める。そうなれば、アーチに入れるけど…手後れか。
シャツの中まで濡れた制服を見て、さらに開き直り半分、情けなさ半分でいると「傘持ってない人、入りなさい」 列の先端の方、アーチの下にいる一人のオジサンが怒鳴っているのが聞こえた。怒鳴ってもなかなか聞こえないほどの雨で、ぼんやりとしていた私は気付くのに時間がかかった。
ここまで濡れたら、入ったって無駄だよ。それに、私がアーチの中に入ったら、他の人まで水がかかるかもしれない。 聞こえないふりで周りを観察していると、何人かの傘がない人は入っていったようだった。
「ほら、そこのお嬢さんっ、まだ空いてますから!」
動こうとしない私にオジサンは再度、声をかけてくれる。私はそれに怒鳴り返した。
「もういいです、ビチャビチャですからっ!」
オジサンは諦めたようだった。私は、今の自分の言葉で、さっきから(傘を差しかけようか)と悩んでいるかのように、こちらをチラチラうかがっている周囲の人が、自分を忘れてくれることを願った。
それからしばらく経った。
図書館で借りてきた本も読めず、することがないまま私は何気なく、バスが来るだろう方向を見た。そして、何かが妙なのに気付いた。薄黄色に濁った空、前が煙るほどの激しい雨。だが、その空の色が、雨の色が変わっている。
予感に、そっと見上げる-二本の傘が、列の前後の人から少しずつ傾けられていた。白と青。雨粒が、上からの傘を通した光で色を変えていたのだ。青い玉と、白い玉。
…言葉もなく。
そのさりげなさに、私は何も言えなかった。黙って、その場に何も知らげに、立っていただけだった。そして、そのままバスに乗った。
今では、それでよかったと思っている。礼を言ったり、気付いたそぶりを見せれば、互いにきまずいだけだろう。あの雰囲気が、台無しになる。
沈黙に見た雨は、綺麗だった。色が白と青に微かに染まっていたし、なにより優しかった。
この日見た雨粒が、私の真珠だ。
(「パール・エッセイ集」の作品より)