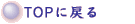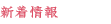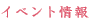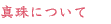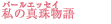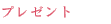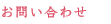|
◆「咲ちゃん」 かみながれい
私の手のひらに小粒な真珠の指輪が載っている。
その頃、私たちはT市に住んでいた。T市は空知川の辺りの静かな田園都市である。
咲ちゃん一家が隣へ引っ越してきたのは、長い戦争が終わって三年目の春だった。
彼女は小学五年、二年生のトモ君と母親の郁代さんの三人家族で、坑内夫のご主人はT市の近くのA炭鉱で爆発事故に遭ったという。
私は咲ちゃんと同じ歳でクラスも同じこともあって、母にそれとなく隣の様子を尋ねられるが、咲ちゃんはひどく無表情、無口ではっきりとは分からない。ただ郁代さんは病気持ちらしく、時々臥せっているらしい。
夏になり田植えが済むころ、郁代さんが働き口はないか、と家に相談に来た。
薬局を営んでいる父が、郊外の野菜農家の手伝いを紹介したが、やはり無理だったらしい。半月ほどして仕事先で倒れた。医師の診断では、肺の患いがかなり進行しているといが、二人の子を抱え、わずかな炭鉱の見舞金の暮らしでは転地療養も難しい。
母が郁代さんから聞いた話では、東京の下町で町工場の事務員の独り暮らしをしているうち、同じ職場の工員と結婚。そのご主人は軽い結核を病んでいたという。やがて戦況が激しくなり、空襲で家も工場も焼かれ、親子四人着の身着のままA炭鉱に流れてきたというから、道内には身寄りはなく、徳島にご主人の叔父さんがいるらしい。
食糧事情の悪いころだが、T市は余裕がある。母が団子やおはぎをおすそ分けに届けると、郁代さんんはひどく恐縮して言葉少なに辞退するとかで、いつしか私が代わるようになった。木枯らしが吹く時分、母が見かねて毛糸の手袋を編んでやると、真っ赤に腫れたヒビだらけの手にはめて、姉弟はぺこんと頭を下げる。父も家の物置に眠っていたストーブを取り付けてやったり、朝の雪かきもしてやる。そんな度に、郁代さんは目に深沈としたものを湛えて深々と頭を垂れるのが常だった。
私も子供なりに気を遣って、教室で咲ちゃんの手提げに新しいノートや鉛筆を忍ばせておくと、いつの間にか机中に返されている。そんな咲ちゃんも算数がずばぬけて良く、私は宿題を携えて隣へよく行く。お礼に少女雑誌を貸すと、胸に抱いてにっこりする。
北国の冬は厳しい。郁代さんの容態はさっぱり快方の兆しがなく、大寒に入ってすぐ、咲ちゃんに呼ばれた母が慌てて自宅に舞い戻って電話で医師を呼んだが、もう遅かった。
通夜は咲ちゃん姉弟と私の一家の五人で、野辺の送りの日は吹雪が荒れ狂っていた。
T市に孤児院はない。とりあえず母が徳島の叔父さんの居所を捜し、父は市の係りと相談して、当分、姉弟を家で預かることにした。二人は夕食を済ますと、今夜からこの家で寝たら、という私達の申し出に無言でもじもじしていたが、やがて我が家へ帰って行く。火の気がなくても母親のぬくもりが残っているのだろうか、次の日もそうだったが、思い通りにさせたら、と父が言う。母は徳島へ手紙を出したが、当てにはしておらず、姉弟が成人になるまでは手元で育てようと心に決めていたようである。ところが二ヵ月程して、徳島の叔父さんが訪ねてきて、姉弟の身柄を引き取るという。
別れの朝、駅のホームで私が姉弟にぼんやり視線を投げかけていると、出掛けに母が編んでやったポニーテールを揺らして咲ちゃんが駆け寄ってきて、「おばさん、これ」と、母に掌を差し出す。見ると手のひらに真珠のリング、結婚指輪らしい。
「これ、母さんから」と声がかすれる。
「いらないわ、大事な形見でしょ」
「ううん、おばさんにって」
列車が入ってきた。時間がない。母が
「じゃ預かるわ、あんたがお嫁に行く日まで預かるわ」と、デッキの咲ちゃんの背に声をかけると、咲ちゃんはひょんと振り向き、「おばさん」と声を詰まらせ、ぺこんと下げた頭を上げると、みるみる両眼にがあふれ出した。
わたしが初めて見る咲ちゃんの涙だった。
その後咲ちゃんから便りが何度かあったが、四年ほどして音信がぷっつり途絶えた。手紙を出しても宛先不明で戻ってくる。何があったのか、風の便りもなく、ともかく生きていさえすればいつか、と母と語り合っているうちに歳月が流れた。
母は時折、それを手のひらに、ぼんやりともの悲し気に見入っていたが、その母も今は亡い。
今、私の手のひらにあるこの何の変哲もない白い光沢は、今までどれほどの人の世の別れを見つめ、人の語ろうとしても語れない心の内を眺めてきたことか。私は真珠という真珠に出会う度に、その無垢な輝きにみるみる想いがあふれて、つい佇んでしまうのである。
(「パール・エッセイ集Vol.2」の作品より)