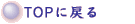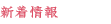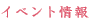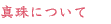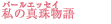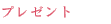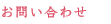|
◆ハルコさんの真珠
入院した日、母はベッドの上で、手術なんかイヤだとダダをこねた。
「隠したってわかる、私はガンなんでしょ?もうムダなことはやめて、頼むから家で死なせてちょうだい」
困り果てている最中に、突然隣のベッドのカーテンが勢いよく開かれた。
「手術がムダですって?冗談じゃないわ!私は胃ガンだけど、必ず治って退院するつもりなんだから!」
それがハルコさんとの強烈な出会いだった。
一瞬見せた激情とは裏腹に、彼女は笑みを絶やさないおだやかな人だった。
いつも編み棒を動かしているので、虹色の刺しゅう糸や温かそうなモヘアが広げられたベッドは、その名のとおり春の野原に変わる。
おばあさんの膝掛け、小児科病棟の子供の手袋、夜勤の看護婦さんのケープ…ひっきりなしの注文を、ハルコさんは魔法のようにこなした。私の肩幅を測った翌日にはもうカーディガンができあがる、という具合に。
その中でいつも後回しにされているニットがあった。ふわふわのピンクの毛糸にパールのビーズをひとつ通して一目編んで、またパール、という調子でなかなか仕上がらない。
「凝ったデザインですね、だれのセーター?」
私がたずねると、ハルコさんはいたずらを見つかった子供のように舌を出した。
「えへへ、ナイショ!」
どうやら秘密の作品らしい。
ハルコさんには高校生と大学生の息子さんがいる。交代で夕方枕元に現れる彼らは口数も少なく、ぶっきらぼうな印象だった。
ある夜、洗濯室に入ると、下の息子さんがひとりでさらしや下着をすすいでいた。私に気付き、軽く会釈をしたその目は真っ赤に腫れ上がっている。…患者の家族の気持ちは、皆同じだ。私は黙ってその場を離れた。
───ハルコさんの手術の日がやってきた。
「行ってくるわね」
ストレッチャーの上で彼女は気丈に笑ったが、顔は青ざめていた。きゃしゃな指で息子さんたちの大きな手を何度も握り締める。
ハルコさんがICUに戻ってくるまで、同室の患者たちは廊下を行ったり来たりした。
「あの人なら、大丈夫」
そう断言したのは、寝たきりでもう何年も入院している加藤さんだった。アンタが言うんなら、とみんなようやく落ち着いた。
ハルコさんは、手術の翌日からひとりでトイレに起きて主治医を驚かせた。めきめき顔色が良くなって退院が近付くのを、私たちは何となく複雑な思いで眺めていた。
退院の朝、彼女はピンクのセーターに着替えた。星のように散りばめられたパールのビーズ。編み込みの白猫の首輪もパールだ。それにはハルコさんの夢が編み込まれていた。
…この日のためのセーターだったのだ。
愛らしい少女のように頬を染めた彼女は、見送りの一人一人に丁寧に頭を下げた。
そして病室はひどく寒いものになった。
───手術の日。不安に怯えきった母に、今さら何を言えばいいのだろう。運ばれる直前、
「あぁ、良かった、間に合った!」
場違いなほど明るい声を響かせて、ハルコさんが風のように病室に入ってきた。
彼女は母の頬に軽く触れ、耳元で何かささやいた。意識のもうろうとした目が少し開く。
「頑張っていらっしゃい」
まるで子供に言い聞かせるようなやさしい声に、母はコックリとうなずいた。その一瞬、私が感じたのは嫉妬だったかもしれない。
手術室のベンチは、ひんやりしていた。
あの時と同じピンクのセーターのハルコさんの耳たぶには、つつましやかなパールのイヤリングが輝いていた。私の視線に気付くと、彼女は照れたように肩をすくめた。
「息子たちが買ってくれたの、たまには本物の真珠をつけろって」
きらびやかな宝石のショーケースの前でうろうろする口下手な彼らを想像して、私はつい笑ってしまった。
「ね、おかしいでしょ?」
ハルコさんも笑う。春の陽がパッと射した。
…母はきっと治るだろう。そして、またこんなふうに一緒に笑えるだろう。
明るい予感だった。なのに涙があふれた。
手術は無事に終わり、母はきっかり二十日後に退院した。必ず来るから、と約束したハルコさんは、その日とうとう現れなかった。
冬の雲間からのぞく太陽は、暗い貝の内側で柔らかい光を放つ真珠に似ている。北風さえ息をひそめる静けさに、ハルコさんのはにかんだ微笑みをふと恋しく思う。
きっと今も、せっせと春色のセーターを編み続けているに違いない。
(「パール・エッセイ集Vol.2」の作品より)