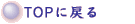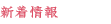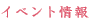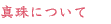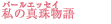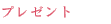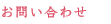|
◆はじまりの一歩 岡本千春
私、十一回。
主人、十三回。
同じ映画を見た回数、ではなくて結婚までに重ねた見合いの回数です。
昨今の結婚条件の厳しさを思えば、私なんて割れ鍋ですからもらって下さる方がいればどんな方でも。なんて謙虚を装っていてもそれはそれ。いざとなれば建前と本音、理想と現実。なかなかに噛みあわないものです。
十一回目、主人との出会いも、第一印象は、ネクラ、無口、いかにもモテそうにない奴、こりゃあ×(バツ)だ。
主人は主人で、気が強そう、男を寄せつけない雰囲気、この歳まで残っていたのがわかる。
お互い共が○印といえず、私にすれば即、断わるつもりが、
無口なんです→必要なことしかしゃべらない、男は黙ってに限ります。
ネクラで……→男のヘラヘラしているのは安っぽくてみっともない。
ふむふむ。物は取りようで言葉は飾りよう。
仲人の口車に乗って、さほど乗り気でもない二度目のデートへ出かけた。
デート場所は、別府ラクテンチ。
福岡出身だが八幡浜に居を構える主人と、福岡の私とでは、デートするにはそこしかなかった。
その日、私の気持ちを見抜くよう生憎の雨。しかも人影はまばらで、気分的にもいまいち盛り上がらなかった。
よし、家に帰ったら仲人が何と言おうと絶対に断わろう。生まれも育ちも福岡の私にとって、四国はやはりちと遠い。そんな海を渡った見も知らぬ外国のようなところへ行くのは嫌だ!と心に決めていた。
別府から帰りの特急列車に乗り込むまでの三十分、何げなく主人に誘われ駅前の喫茶店に入った。
これがサイゴのお勤め、とばかりの私に主人から渡された青いビロードの箱。
「?」
恐る恐る開けてみると、一粒真珠のついた銀のブローチ!
「僕のほうは……あの……いいですから……そちらさえ……その……よければ……」
これが主人のプロポーズの言葉だった。
・僕と一緒に人生を歩いて行こう・、・毎朝、あなたの美しい声で起こして下さい・、なんてドラマのようなプロポーズを夢見ていたわたしにはそんなのありィ……の拍子抜けだった。それなのにふと気がつけば、断わるはずの見合いを、・私でよければ・と返事してしまっていた。
それから結納、結婚はあっという間で、いつのまにか私は、この愛媛の地で暮らし始めている。
あの宮さんだってダイヤモンドに目が眩んだんだ。私ごときが真珠に目が眩んだとしてもおかしくはない。主人には内緒だが、本音を言えば、ちょっぴり早まったかなぁなんて思うときもたまにある。
「私がイエス、って言う保障もないのに、どうして高い真珠のブローチなんて買ったの?」
「イチかバチかに賭けてみたんだよ」
「もし、ノーだったら?」
「その時はその時。高いプロポーズ代についたと思ってあきらめてたよ」
主人のイチかバチかに賭けた真珠のブローチは、幸いなことに私の手元に渡ってきた。
今、一粒の真珠は、私たち二人を夫婦にし、さらに三人へと家族を増やしていった。
これから先、またどのくらい、またどのように膨らんでいくのだろうか?
ときおり、人の縁(えにし)の不思議さを思うとき、この青いビロードの箱を開けてみる。
もしあの時、特急列車の待ち時間がなかったら、プロポーズに添えてこの真珠のブローチをもらわなかったら、また違う人生を歩んでいたのかもしれない。
思い迷う私に、一粒の真珠は自ら選んだはじまりの一歩が、決して間違いではなかったといつも輝いてくれる。
(「パール・エッセイ集Vol.1」の作品より)