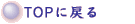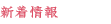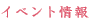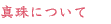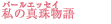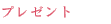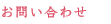|
●用語説明
| 核 (カク) |
米国の淡水産2枚貝の貝殻を丸く削って作った玉で、真珠の中心にあり、真珠の大きさを決める最大の要因。 アコヤ真珠用としては、直径1.81ミリ~9.09ミリ。南洋真珠用では18.8ミリまである。 |
|---|---|
| ピース (外套膜の切片) |
外套膜(ガイトウマク:貝殻を作っている器官)を小さく切ったもので核とともに母貝の体内に入れる。この外套膜の切片は核のまわりに袋状に広がり、真珠袋を形成して核に対して炭酸カルシウムの結晶(つまりは貝殻の内側の光っているもの)を積み重ねてゆき、これが真珠となる。 核が無くても真珠袋ができれば真珠はできる。淡水真珠は核を入れずピースを入れるだけでつくられている。 |
| 真珠層 (シンジュソウ) |
真珠袋によって作られた核のまわりの炭酸カルシウムの結晶(アラゴナイト結晶)の重なりのことで、真珠の表面に当たった光は中を透過しながら屈折と反射を各層において繰り返す。 これによりまるで内側からも光っているように見える(多層膜干渉という現象)真珠の輝きの主因。 |
| アラゴナイト結晶 (アラゴナイトケッショウ) |
真珠層を形成する炭酸カルシウムの結晶。 六角形の薄い板状(アラゴナイト型=霰石(アラレイシ)型)で1枚の厚さが1万分の3.5~4ミリ前後と薄く、コンキオリンという蛋白質のシートをはさんで幾層にも重なっている。この結晶一枚の厚さが真珠の干渉色に影響する。 |
| コンキオリン | アラゴナイト結晶をつなぐ蛋白質。 これが多いとアコヤ真珠の場合黄色が強くなりやすい。わずかな水分を含んでおり急速に乾燥すると輝きを失う原因となる。 |
| 浜揚げ珠 (ハマアゲダマ) |
真珠母貝から取り出して表面を洗っただけの無加工の真珠。 この状態で愛媛県漁連の入札会に出品され、各メーカーに販売される。 |
| エンハンスメント (改良:カイリョウ) |
真珠が有する潜在的な美しさを引き出す目的で一般的に行なわれている軽度な加工処理で、加温・漂白・調色がある。 販売時での表示は国際貴金属宝飾品連盟(CIBJO)によって不要とされている。 |
| トリートメント (改変:カイヘン) |
真珠が有する本来の性質とは関係なく、人工的に色や外観を改変する強い加工で、染色・着色・放射線照射がある。 販売するときは、表示していなければならない。 |
| 加温 (カオン) |
真珠に適当な熱を加え、真珠中の色素の除去、あるいは光沢の改良を行なうこと。 |
| 染み抜き・漂白 (シミヌキ・ヒョウハク) |
浜揚げ珠は個性が強く様々な色を持っており、母貝の有機物によるシミのあるものも多いため、穴をあけて弱い漂白を行なう。 |
| 調色 (チョウショク) |
染み抜きによって失われた色を補完するため真珠の中に薄い赤色系色素を加え、極めて軽度に真珠の色相を調整すること。 |
| 無調色真珠 (ムチョウショクシンジュ) |
調色する前の真珠。真珠層が厚く、その構造が整然としたものでないと美しくない。 アラゴナイト結晶を繋いでいる蛋白質であるコンキオリンの色がそのまま出るので薄いクリーム系のものが多い。 |
| 無調色真珠 (ムチョウショクシンジュ) |
調色する前の真珠。真珠層が厚く、その構造が整然としたものでないと美しくない。 アラゴナイト結晶を繋いでいる蛋白質であるコンキオリンの色がそのまま出るので薄いクリーム系のものが多い。 |
●品質を決める要素
| 巻き | 真珠層の厚さのことで、これが薄いと美しい輝きが出ない。しかも短期間で輝きが失われる。 |
|---|---|
| テリ | 真珠の輝きのこと。 真珠層が厚く、その構造が均一で珠の表面が緻密で滑らかであり、アラゴナイト結晶一枚の薄さが適度であるとテリが良くなる。 |
| キズ | 珠の表面のシワやへこみ(えくぼ)、突起などのこと。巻きジワとか巻きムラとも云う。 巻きの厚い無傷は少ない。 |
| 色 | ホワイト・ピンク・クリーム・ブルーなどがあり、 ①光の干渉現象 ②コンキオリンの色素 ③核表面の有機質 ④調色 これらが色の決定要因で、特に①の光の干渉現象による色は強い光線下と弱い光線下では大きな差が出る。 染めたり放射線をあてたりして作ったグレーやブルー・グリーンもある。 |
| 形 | ラウンド(形が完全に丸いもの)が良いがドロップやバロックも個性的で人気がある。 |
| 大きさ | 上記の各品質が同等ならば大きい珠は高い。 母貝に大きい核を入れると巻きにくく死に易いので、巻きの良い大珠は希少。 |
| 鑑別書 (カンベツショ) |
宝石が本物か偽物かを鑑別して表示した書類。 真珠製品の場合、鑑別した真珠製品の写真とともに真珠の種類・珠の大きさ・金具の金性(14金か18金か等)・加工(染めとか放射線照射とか)の有無等を表示している。加えて、それぞれの民間鑑別機関独自の基準で評価したグレーディング(等級付け)を表示しているものもある。 |
| 鑑定書 (カンテイショ) |
宝石を鑑別した上に品質を評価した書類。 ダイヤモンドのグレーディング(4C)が有名。ダイヤモンド以外の宝石は国際的な評価基準が定まっていないため鑑別書となる。 |
●真珠の種類・名称
| 花珠 (ハナダマ) |
本来は生産者の言葉で、ラウンド(真円)、無傷で巻きが非常に厚く、すばらしいテリのある、好ましい色(薄いピンク)を発色するトップクラスの浜揚げ珠のこと。 現在は製品販売のセールストークに使われているが、明確な基準は無く販売店や民間鑑別機関が独自の判断で呼称しており同じ花珠でも品質に大幅な違いがある。 |
|---|---|
| アコヤ真珠 [アコヤ貝養殖真珠] (アコヤシンジュ) |
愛媛、長崎、三重、熊本を主産地とする日本産養殖真珠の代表で、繊細で強い輝きをもつ真珠。 外国産に対して和珠とも言う。色には、ホワイト・ピンク・ブルー・グレー・クリームなどがある。 |
| 白蝶真珠 [白蝶貝養殖真珠] (シロチョウシンジュ) |
オーストラリアやインドネシアなどで養殖される、柔らかい輝きの大珠真珠。 色はホワイトやゴールドなど。南洋白真珠とも言う。 |
| 黒蝶真珠 [黒蝶貝養殖真珠] (クロチョウシンジュ) |
仏領ポリネシア(タヒチなど)を主産地とする真珠で、多彩な色があり神秘的な輝きを持っている。 色はブラック・シルバーグリーンなどがあり、ピーコックグリーンと呼ばれるものが最上とされる。南洋黒真珠ともいう。近年チョコレート色に加工されたものも市場にでている。 |
| マベ真珠 [マベ貝養殖真珠] (マベシンジュ) |
奄美大島やインドネシアで養殖される真珠。 貝殻の内側に核を貼り付けて養殖する為、半球形の真珠となる。良いものは美しい虹色の輝きを持っている。 近年真円養殖技術が確立された。 |
| 淡水真珠 [淡水産真珠貝養殖真珠] (タンスイシンジュ) |
主に中国で養殖している真珠で、池や川などで養殖されているので淡水真珠と呼ばれる。 ピースを入れただけで養殖するため、核が入っていないので比較的小さく、色も形も様々で価格も安く気軽につけられる真珠。母貝はヒレ池蝶貝など。 |
| アメリカ淡水真珠 (アメリカタンスイシンジュ) |
米国で養殖されている淡水真珠で扁平な核(コイン型やハート型など)を入れたものがある。 母貝はカワシンジュ貝など。 |
| 天然コンクパール (テンネンコンクパール) |
カリブ海で採取される大型食用巻貝のピンク貝の中から非常にまれに出てくる天然真珠。 ピンク・ホワイト・クリーム・オレンジなど多彩な色があり、なかでも火炎模様や絹のような模様の現れているものが最上とされる。 |
| 天然アワビパール (テンネンアワビパール) |
米国や日本、メキシコなどでアワビからまれに採れる真珠。 色は青緑色やグリーンやクリームなどで強い輝きを放つ。貝殻の内側にくっついて見つかるものが大半。 |
| その他の天然真珠 | ホースコンク真珠・ピピ真珠・ホンビノスガイ真珠・メロ真珠・天然アメリカ淡水真珠 など |
●形の種類
| ラウンド | 完全に丸いもの |
|---|---|
| セミラウンド | わずかに丸くないもの |
| ドロップ | しずく型のもの |
| オーバル | 楕円形のもの |
| ボタン | ボタン形のもの |
| セミバロック | 少しいびつな形のもの |
| バロック | いびつな形のもの |
| ドラゴン | 淡水真珠の奇怪な形となった大きいもの |
| ライス | 淡水真珠の米粒のような形のもの |
| サークル | 数本のくびれがあるもの |
| ケシ | 芥子つぶのように小さい真珠で養殖の副産物として自然にできたもの 現在は無核の自然にできた真珠全般を云い南洋真珠のケシのように大きいものもある。 |
| スリークォーター | 丸い珠の一部を削ったもの |
| ツイン | 母貝の中で二つの真珠が自然にくっついたものと、スリークォーター同士を接着したものがある。 |
| ハーフ | マベパールのように半球形のもの |
●ルースの種類
ルースとは、金具などをつける前のバラ珠のこと。
直径で分けており、通常0.5ミリ間隔で標記している。大きい珠は一個ずつ実測値を表示している。
| 無孔 (ムアナ) |
穴があいていないルース |
|---|---|
| 片孔 (カタアナ) |
穴が貫通していないルース |
| 両孔 (リョウアナ) |
穴が貫通しているルース |
| 半形 (ハンケイ) |
半球形のルース |
| 3/4ルース |
キズや突起を削って 3/4球形にしたルース |
| ペアルース |
イヤリングやピアス用に色やテリ、大きさを合わせた2個のルース |
●ネックレス用語
| 連組 (レングミ) |
両穴珠を品質を揃えて糸を通すこと。 端を小さく真ん中を大きくし通常40cmに組む。 |
|---|---|
| 連相 [マッチング] (レンソウ) |
ネックレスの珠の色・テリなど品質の揃いかた。 選別と連組の技術が高くないと連相が悪くなる。あえて連の中にまったく違う色を入れてデザインしているネックレス(マルチカラー)もある。 |
| 通糸連 (ツウシレン) |
連組されたネックレスで金具をつける前のもの。 |
| ロット | 同じ品質の通糸連のたば。業者間はこれで取引されている。 |
| クラスプ | 通糸連につけるネックレスの留め具。様々な種類がある。 |
| ユニフォーム | 珠のサイズ差が0.5mm以内で組まれた基本となるネックレス (例 7.0mm以上7.5mm未満) 長さ(留め具を含まない)で呼び方が変わる。 ・カラー 約30~33cmのユニフォーム ・チョーカー 40cm前後で冠婚葬祭に使われる一番多い長さ。プリンセスサイズと呼ばれることもある。 ・マチネー 約53cm ・オペラ 約71cm ・ロープ 約107cm ・ロングロープ ロープより長いもの |
| グラデーション | ネックレスの中央の珠を一番大きい珠として端に行くほど小さくすること。 ユニフォームより珠の大きさの差が大きいネックレス。 |
| 取り珠 (トリダマ) |
長さを調節するため、ネックレスから珠を取って短くすること。 |
| 珠足し (タマタシ) |
ネックレスの長さを少し長くするために珠を加えること。 |
| 糸組 (イトグミ) |
GPT(高密度ポリエチレン)・テトロン・ナイロン・絹糸などを通してネックレスにすること。 |
| ステンレスワイヤー組 | ステンレスワイヤーを通してネックレスにすること。 伸縮性が無いため、ラインが硬くなるので通常柔らかいラインを出すためにシリコンラバーの小さいクッションを珠と珠の間に入れる。 伸縮性のある糸の場合は緩まないよう最後に糸を強く引いて組み上げるが、そのとき形がいびつなバロック珠は、それぞれの珠が思い思いの方向に向いてしまい、ラインの中心からはずれてしまうため大半のバロック珠ネックレスはこれで組む。 |
| オールノット | 全ての珠と珠の間に結び目を入れる組方。 もし糸が切れても失う珠が最小限で済む。珠と珠の間にすきまができることで敬遠され、切れにくいナイロン糸などの登場で少なくなった。 |
●お手入れと保管
真珠は、炭酸カルシウムの結晶とそれを繋ぐわずかに水分を含んだ蛋白質でできています。
ネックレスの糸は、伸びて緩んだり珠の穴口でこすれて切れたりすることがあります。
したがって、
① ほかの宝石や金具類より柔らかいので、硬いものと擦れあわないよう保管や運搬をしてください。
② 酸性の液体に長く触れると表面の結晶が溶けてテリが弱くなりやすいので、使ったら柔らかな布でよく拭いてからしまってください。
③ 急速に乾燥すると真珠層の構造が崩れて輝きが鈍くなりやすいのでストーブのそば等に長く置かないようにしてください。
④ 揮発性の薬品の影響を受けて変色することがあるので、防虫剤・芳香剤・香水など揮発性の薬品の影響下で長期間保管しないようにしてください。
⑤ ネックレスの糸は水分で伸びたり、珠の穴口で擦れて弱くなるので、使用頻度や糸の種類にもよりますが、2~4年に一回は糸替えをしてください。
ステンレスワイヤーの場合もナイロン被覆が傷んだり、珠の間のシリコンラバーが無くなったりすることがあるので糸替えが必要です。
でも、余り神経質になることもないです。
案外丈夫な宝石で、特に、 靱性 (ジンセイ:ねばり強さ、外力によって破壊されにくい性質)が高いので割れにくく、巻きの厚い真珠なら拭いてさえいれば長く輝きを保ちます。
糸は毎年替えることが望ましいのですが、GPT(高密度ポリエチレン)やテトロンなら非常に強く、4年で切れることはまずないでしょう。糸の切れる前兆は、緩みと毛羽立ちですから使う前にチェックしてください。
拭き布は、柔らかい布であれば何でも良いのですが、専用の布(非常に細い繊維で織られた布など)も売っています。
真珠はちょっとしたお手入れや心使いで長く輝きを保ちます。